6 「富岳」の利用拡大等に向けた取組
6-3 Society 5.0実現に向けた貢献
我が国が世界に先駆けてその達成を目指すSociety 5.0においては、サイバー空間に社会のあらゆる要素をデジタルツインとして構築・解析し、最適な解(ソリューション)を求めた上で、フィジカル空間の制度、ビジネスデザイン、都市や地域の整備などに反映することにより社会を変革していく「サイバー空間とフィジカル空間の融合」が求められる。この実現のために、⾼度な解析を可能とするデータ解析技術と大量のデータを扱うスパコンが必要となる。
「富岳」は、総合科学技術・イノベーション会議での「フラッグシップ2020プロジェクト(ポスト「京」の開発)」の中間評価において、「Society 5.0における研究開発基盤として生かされるよう他府省間や大学、研究機関間での連携をはかること、Society 5.0において重要となるビッグデータ、AI等のアプリケーションについても高い性能を有することを確認すること」と指摘されている。
このように、「富岳」は「サイバー空間とフィジカル空間の融合」を実証する研究開発基盤と位置づけられている。
さらに「富岳」は、後継機に向けて、スパコンを「計算のためのツール」から「社会変革のためのインフラ」へと着実に進化させることが期待されており、これにつながるように研究開発等に取り組んでいくことが必要である。
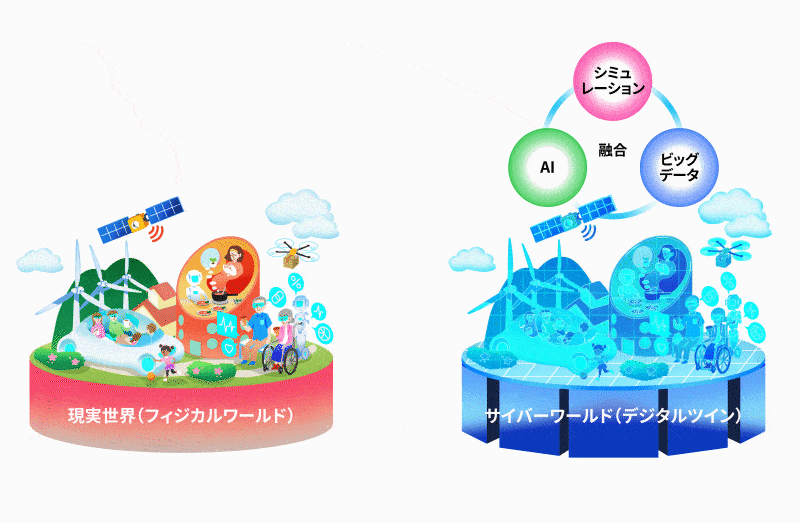
2022年度Society 5.0推進拠点においては、前述の〈クラウド上での「富岳」環境の実現〉に参画するともに、2021年度に引き続き、Society 5.0実現に資するための多角的な活動(推進拠点の体制強化、個別プロジェクトメイキングやプロジェクトマネージメントの実施、及び「富岳」潜在的ユーザーの掘り起こしとユーザー拡大)を行った。また、様々な科学技術分野や業種業態においてSociety 5.0の実現に向けた挑戦が多様に行われているが、それらにはスパコンや物理シミュレーションを有効活用しないものが多いという現状に鑑み、R-CCSが目指す次世代のSociety 5.0社会の実現に向けて、「富岳」をはじめとするハイパフォーマンスコンピュータが果たす役割や、取り組むべきことについて検討、整理した。さらに、「富岳」の波及効果やユーザー目線で見た問題点の抽出を行うべく、外部調査会社を利用した分析を行った。
6-3-1 「富岳」Society 5.0 推進拠点の設置推進体制強化
2021年度に設置された「富岳」Society 5.0 推進拠点においては、2022年4 月から大手企業における研究・研究管理、HPC利用経験のあるコーディネーターを増員し、プロジェクトメインキング及びプロジェクトマネージメント業務の実施体制の強化を行った。また2021年度に引き続いて「『富岳』Society 5.0 推進利用課題の支援業務」に関する外部委託を行い、民間ノウハウを活用して研究者や企業とのきめ細やかなプロジェクトメイキングを行った。
6-3-2 新型コロナウイルス対策を目的としたスーパーコンピュータ「富岳」の優先的利用
2020年の「富岳」試行利用時の当初に開始された新型コロナウイルス対策のための研究について、2022年度も継続して「富岳」を活用することで、コロナウイルスのスパイクタンパク質における構造変化の予測に成功するなど科学的成果をあげることができた。
6-3-3 地元自治体との連携
兵庫県及び神戸市からの補助を受けて実施する研究開発拠点(COE)形成推進事業において8件の研究課題を実施し、神戸市の政策ニーズを踏まえ新規サブ課題として「将来の暑熱環境の変化シミュレーション」を立ち上げた。また、SPring-8/SACLAの大規模データを活用するためのAIによるデータ圧縮の基盤技術の開発など兵庫県にある大型研究施設との連携を進めた。これらにより創出された「Society 5.0の実現」に資する研究成果については、地元自治体にその成果を還元し、地域の課題解決に貢献する等の観点から、成果の公表、アウトリーチ等を行った。
さらに、神戸市、NTTドコモと連携協力の覚書を締結し、「都市計画や防災計画に資する、「富岳」を活用したデジタルツインシミュレーション」の社会実装に向けた取り組みを開始した。2022年度に再整備の進んでいる神戸市のウオーターフロントエリアにおける群衆移動の基礎シミュレーションを実施し、阪神・淡路大震災の節目となる2023年1月17日にプレスリリース及び動画配信を行った。
また神戸大、兵庫県立大、神戸市を中心とした産学連携の新規プロジェクト構想「データドリブン型未来健康共創社会拠点」に参画して、JST「共創の場」への申請を行った。あいにく採択には至らなかったものの次年度の採択を目指して神戸大、神戸市との協議を継続した。
6-3-4 プロジェクトメイキング及びプロジェクトマネージメント
(1)創薬 DX プラットフォーム
2021年度に新設された「富岳」Society 5.0推進利用課題枠への応募(申請者:一般社団法人ライフインテリジェンスコンソーシアム(LINC))を R-CCS、京大院医学研究科、医薬基盤研、LINC四者の連携協定の下で支援し、2022年6月に採択された。この採択に伴い、創薬DXプラットフォーム構築を推進するために、四者連携協定に基づく共同研究契約を締結し、「富岳」上でのプラットフォーム構築のために理事長裁量経費を獲得し、創薬DXプラットフォーム上に搭載するアプリケーションの「富岳」への実装とワークフロー構築等の取り組みを推進した。
(2)大阪・関西万博への協力
大阪・関西万博を「富岳」の価値を社会に示す機会ととらえ、2021年度に引き続き、万博の会場運営支援(会場内混雑シミュレーション、発災時を想定した避難誘導方策、感染症リスク対策等)の提案を万博事務局に行い、調整を継続した。
また総務省の政府アクションプラン「リモートセンシング技術による高精度データの収集・分析・配信技術の開発」において、 NICT、防災科学研究所、大阪大学と連携し、リモートセンシング技術を活用した高精度降雨予測を行い、来場者や運営スタッフ等へ情報提供するための取り組みを開始した。
万博展示に関しては、テーマ事業「いのちを拡げる」のプロデューサー石黒浩氏が主導するシグネチャーパビリオン「いのちの未来」において、「富岳」を使った人間の全脳シミュレーションの展示を行うべく、調整を進めた。また、国土交通省の政府アクションプラン「熱中症や高潮浸水の高解像度物理シミュレーションによる早期の情報提供」は、都市丸ごとのシミュレーション技術組合が実施主体として提案されたが、この企画においてR-CCSは同組合との共同研究により「富岳」を用いた高潮シミュレーションを実施する方向で調整を進めた。
6-3-5 「富岳」潜在的ユーザーの利用拡大のための技術的・制度的課題等の洗い出しと対応
「富岳」の利用を検討しようとしている潜在的なユーザーの発掘や、ユーザー候補者の「富岳」利用の障壁を下げることを目的に、関係機関(文科省、RIST)と協力して立ち上げた「ポテンシャル・ユーザー対応WG」を、引き続き2022年度も複数回開催した。「富岳」の有償利用の手続き簡略化をはじめとする利用制度上の課題について議論を行い、特に有償利用における諸々の制度面の改善提案や申請簡素化の提案を行った。また、ファーストタッチオプションの産業界向け利用マニュアルの内容拡充とアップデート、「ファーストタッチオプション・クイックスタートガイド」を公開した。
6-3-6 外部調査による「富岳」の客観的評価
「富岳」構築による波及効果の経済的評価やユーザー目線での問題点の抽出を客観的に行うことを目的とした調査分析を、ハイペリオン社に委託した。「富岳」ユーザーへの質問に基づく分析が行われ、「京」よりも高い投資対効果が見こまれること、随所に使い勝手の良さがあること、また産業に重要な成果がすでに創出されつつあることなどが示された。一方ユーザー目線としてIO性能などには問題点があることなど、課題も効果的に抽出され、「富岳」高度化やNEXT「富岳」構築に向けて示唆を得た。