研究者に聞いてみよう! 第12回
今村 俊幸 チームリーダー
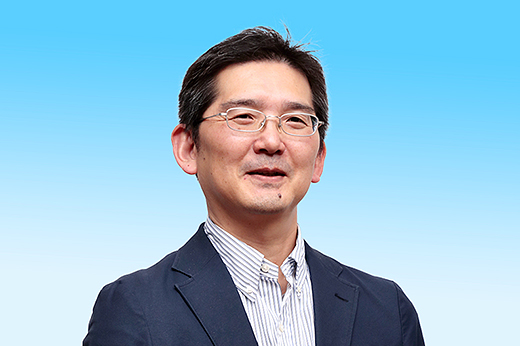

豊岡高等学校の皆さん
―理化学研究所のスーパーコンピュータ「富岳」は近年、新型コロナウィルスの飛沫シミュレーションなどで活躍している世界的な計算機だ。今回、私たちは行列の固有値計算の研究者として、「富岳」の計算の高速化を実現された今村俊幸先生にお話を伺った。実際に研究を仕事にしている方は、どんな人でどんな風に研究をされているのか?また、計算機科学とはどんな研究フィールドなのだろうか?といった私たちの興味を念頭に、インタビューを行った。
多方面で利用される固有値計算
今村先生の所属されている理研の計算機科学研究センターには20ほどのチームがあり、研究室という単位で研究を進めているそうだ。研究室ごとにテーマが決まっており、各研究室間の連携や、企業、大学研究所、時には海外の研究所との共同研究も行うという。最近「富岳」で行われた飛沫のシミュレーションは、実はエンジンのガソリン噴出のシミュレーションをもとにしているそうだ。研究テーマは、研究者のこれまでの研究背景と共に社会のニーズも考慮して決めていると話してくれた。
今村先生は大学院生の頃から行列の固有値を計算するアルゴリズムを研究されており、かれこれ25年になるという。固有値の計算は、原子や有機化合物など、ミクロな物質の分子レベルの配置等の最適化や、ゲリラ豪雨のシミュレーション、さらにはインターネットのキーワード検索など様々な場面で利用されているらしい。
具体的な計算内容についても、非常に興味深いお話を聞くことができ、より身近に先生のアルゴリズムを感じられた。
先生は「社会的・科学的な課題を計算する際に、スーパーコンピュータ上で数学をうまく活用するためのアルゴリズムやソフトウェアを実現することが重要だ」と考え、研究を進められてきたそうだ。しかし、そこには計算機科学特有の難しさというものがあった。
この近似の影響で誤差が肥大化し、途中で計算が破綻してしまうということがあるのだそうだ。実際に固有値のアルゴリズム開発でも、「数学的には解けるがプログラムで実現することが難しい」という壁が立ちふさがったとおっしゃっていた。
先生はこのような壁にぶつかった際、他の研究者と議論したりして、全く違うアプローチを試みることもあるという。
研究所内の連携や、海外との共同研究のお話と合わせて、他分野、他の研究者との関わりの中で、学問領域が広がっていることを実感できた。そういった、人と関わる技術も研究者には求められるようだ。
このように、様々な分野が交わる領域で互いを理解し、意識のすり合わせをしていく作業は、抽象的な数学を具体的にかみ砕いて、プログラムで表現することにも繋がるのだという。ここには、様々な人、物と関わる中で新しいものを創造しようとする、今村先生の研究者としての誠実さがあった。
そんな今村先生に、研究者として大切にしていることを伺った。
先生の言葉には、研究を職業とする方としての確固たる信念が垣間見られ、それだけ説得力があった。私たちも学校での研究発表の際などに意識をして、「研究」というものに真摯に向き合いたいと思った。
先生は今、「量子計算機」と呼ばれる、新たな計算原理に基づいたコンピュータのアルゴリズムの研究をされている。これを用いれば、先ほど出てきた誤差を減らす新しい手法を取り込むなどして従来よりも圧倒的に速く計算が可能なプログラムが実現できるという。今後の研究の進展が楽しみだ。
研究者の方々の努力、信念が「プログラム」や「アルゴリズム」という見えない形で活躍し、私たちの生活を支えている。そのことを忘れず、研究者の方々に感謝して、日々を過ごしていきたい。
最後に、インタビューを受けてくださった今村先生、本プログラムを企画いただいた計算機科学研究センターの皆様に感謝申し上げます。

第12回 (PDF:33.5MB)
