研究者に聞いてみよう! 第11回
離散事象シミュレーション研究チーム
楳本 大悟 客員研究員
楳本 大悟 客員研究員
研究者に聞いてみよう!
2020年03月掲載
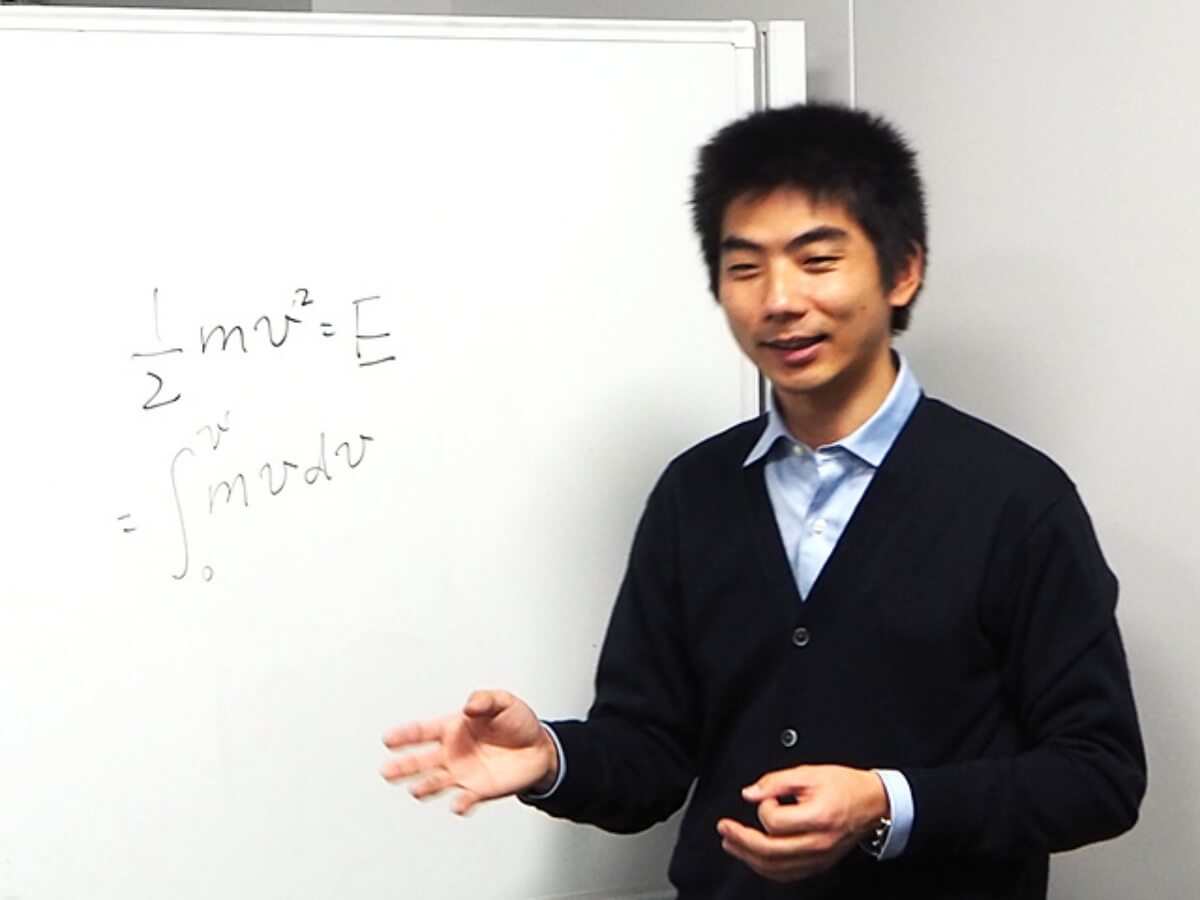
楳本 大悟 客員研究員
Daigo Unomoto
神奈川県立川和高校卒業。
千葉大学・東京大学・理研を経て2019年から神戸大学の特命講師。
趣味は機械加工(旋盤・フライス盤)、音楽、料理など。
大学時代は電子回路設計・制作にハマっていた。最近再開した趣味はヨット。
千葉大学・東京大学・理研を経て2019年から神戸大学の特命講師。
趣味は機械加工(旋盤・フライス盤)、音楽、料理など。
大学時代は電子回路設計・制作にハマっていた。最近再開した趣味はヨット。

私たちが取材しました!
兵庫県立
淡路三原高等学校の皆さん
淡路三原高等学校の皆さん
社会の規則性を科学で
―楳本さんは社会科学者として、シミュレーションを用いて社会の中で起こる物事の規則性について研究しています。社会科学は使い方によっては悪い噂やネット上の炎上など“兵器”にもなりますが、テロ防止や防災にもつながる素晴らしい分野です。「科学法則は“世界のルール”で、科学だけが“世界のルール”を変えることができる」。科学についてそう語り、日々前向きに楽しく研究している楳本さんにお話を伺いました。
(兵庫県立淡路三原高等学校 1年生有志)
研究する中で楽しいことは?
世界の誰も知らないことを自分だけが知っている、という瞬間です。なにかトキメクものがありますね。山登りと同じで、正直そこにたどり着くまでは苦しいけど、達成できた時は最高です。もう一つは自分で作る楽しさです。ある状態を作ると何が起きるのか、という研究をしているので、「どうなるのかな?」と設定を作っている時が楽しいです。結果が想定通りにならなかった時はもっと楽しい! 自分が想像していたより世界がずっと広いことに気付くわけですから。それはもしかしたら、みんなも思い違いをしていたことかもしれない。そんな世界の秘密を自分だけが知っている瞬間があるのは楽しいです。上手くいかないこともありますが(笑)。
上手くいかない時の気分転換は?
取り組んでいることからいったん離れて、別のことをします。おいしいものを食べたり、料理をして気を紛らわしています。他には論説や小説を読んで気持ちを落ち着かせたり、家に友人が遊びに来てくれて話をしたりするのも気分転換になります。研究という趣味性が強い職に就いていると、仕事と趣味が混じってしまい、つまずいた時に全てが辛くなってしまうので、仕事(オン)と趣味(オフ)は分けて、楽しむ時は思いっきり楽しむことが大切ですね。
研究している今だからこそ学生時代にやっておけばよかったと思うことは?
言って大丈夫か分からないんですけど、彼女を作っておけばよかったってことですかね。やっておけばよかったことというよりは、出来なかったことか(笑)。
学生時代はやりたいことをやってきたので、それ以外の後悔はないです。強いて言うなら、もっと勉強をしておけばよかった。学生の時、勉強嫌いだったんですよ。やらなくてはいけないからではなく、楽しいならやるという感じでしたね。当時から好きだった物理は得意教科でした。
学生時代は留学をしたと伺いましたが、言葉の壁をどのように乗り越えたのですか?
話すこと・質問することが重要ですね。知らない単語が出てきた時に調べることも大切です。同じ単語に別々の場面で3回出会うと覚えられます。3~6カ月くらいで英語の文章を書けるようになり、会話するには9カ月くらいかかりました。
話せるほど英語がよく分かってくると、聞き取れるようになります。先に聞き取れるようになるというわけではないんです。話していても、発音が悪いと相手にしてくれず、“はぁん?”と言われますね。相手に伝われば、“あはん”と言ってくれますよ。
これ日本で言ったら喧嘩売っているみたいですね(笑)。今でも英語は苦手ですが、吸収力がある若いうちに留学すべきだと思います。
効果的な勉強方法は何ですか?
いい参考書を見つけて楽しく勉強することですね。義務だと思うとあまり楽しくないし、伸びにくいです。簡単な基礎から極めて、順番に理解していくことが大切だと思います。誰しも「理解できること」は楽しいです。でも勉強を好きになるって難しいですよね(笑)。なので、勉強が楽しくなるように仕向けられるといいと思います。
勉強においてもスポーツにおいても、必要を感じながらやると、分からないことを放っておけなくなるので、効率的にやれると思います。ちなみに私は『直観でわかる数学』(畑村洋太郎著)っていう本を読んだりしていました。続編もあります。
とても面白いのでぜひ読んでみてくださいね。
私たちの学校では理系を目指している女子が多いのですが、女性と男性の研究者で違う点や、女性の方が大変な点はありますか?
私自身は研究に性別は全く関係ないと思っています。ただ、男性目線で言うと、女性は大変そうだなと感じることもあります。結婚や出産、育児には家族や職場の人のサポートがとても大切なのではないでしょうか。
サポートが得られやすいかどうかは研究分野によるかもしれません。私の分野はコンピューターさえあればどこでも研究できますが、実験室に行って実験する必要がある分野はそうはいかないと思います。
ただし全体的に、社会はいま少しずつ良い方向に変化しつつあると思います。
その変化を加速するためにも、そこで仕事を続けることが本当に人生のプラスになるかどうか一人ひとりがよく観察し、しっかり選ぶことが大切だと考えています。ちなみに、理研のサポートは手厚いと聞いていますよ。
インタビューを終えて

この記事は「計算科学の世界」NO.20
に収録されています。
に収録されています。
計算科学の世界 VOL.20
(PDF:3.49MB)

